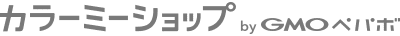| 2014年 | |||
|---|---|---|---|
| 2014年12月号 特集「続・使用済家電等不用品回収業者の実態と対策」 |
|||
| 特集 | 違法な不用品回収業者対策の必要性、最近の動向について | 眼目 佳秀、二木 豪太郎(環境省) | |
| 今後の家電4品目の適正リサイクルについて(家電リサイクル制度見直しの審議会を踏まえて) | 川崎 直也(環境省) | ||
| 都内不用品回収業者に対する立入調査実態報告 | 千葉 裕児(東京都環境局) | ||
| 札幌市における不用品(使用済家電製品)回収業者への対応について | 八田 智宏(札幌市環境局) | ||
| 名古屋市の不用品回収業者対策 | 村本 達彦(名古屋市環境局) | ||
| 岐阜市における不用品(無料)回収業者の逮捕と指導状況について | 鹿嶋 宏治(岐阜市環境事業部) | ||
| 【コラム】廃家電不正流通防止対策の事例報告 | |||
| 一般廃棄物許可業者による適正な不用品回収について | 張田 真(ハリタ金属株式会社) | ||
| ますます膨らむ疑問――「使用済み家電を含む金属スクラップ」の不適正処理問題を取材して―― | 河野 博子(読売新聞) | ||
| 市町村による市民への情報提供について(市民の立場から) | 崎田 裕子(ジャーナリスト・環境カウンセラー) | ||
| 廃棄物等の不法輸出に係る水際対策について | 甲斐 文祥(環境省) | ||
| 輸出規制現場等から見る使用済家電等不用品回収問題 | 吉川 圭子(環境省) | ||
| あかりまど | 不用品回収業者について | 寺園 淳(独立行政法人国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター副センター長) | |
| 調査研究レポート | 感染性胃腸炎の集団発生に係る環境調査事例 | 大柴 知泰(東京都 西多摩保健所) | |
| 連載 | ■環境と経済 | 長谷部 勇一(横浜国立大学大学院) | |
| ■公衆浴場・温泉・旅館業・スポーツ施設・介護保険施設のための〈続〉よくわかるレジオネラ症対策 | 中臣 昌広(保健所・環境衛生監視員) | ||
| ■福島からの情報発信 | 斎藤 隆(公益財団法人福島県国際交流協会 専務理事) | ||
| ■散歩みち | 松葉 清貴(株式会社テクノ中部・元愛知県環境部職員) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2014年11月号 特集「ねずみ・害虫類のIPM(総合的有害生物管理)」 |
|||
| 特集 | IPM理念に基づく環境管理 | 平尾 素一(日本ペストコントロール協会) | |
| 建築構造からみたネズミの侵入経路調査 | 元木 貢(アペックス産業株式会社) | ||
| 適正なゴキブリ指数管理 | 田原 雄一郎(株式会社フジ環境サービス) | ||
| トコジラミ対策に関する調査と防除 | 小松 謙之(株式会社シー・アイ・シー) | ||
| 食品害虫の発生源調査と対策 | 平尾 素一(環境生物コンサルティング・ラボ) | ||
| IPMを取り入れた包括的な有害生物対策について | 関 孝史(株式会社世界貿易センタービルディング) | ||
| IPMの推進に向けた東京都の取組み | 奥村 龍一(東京都健康安全研究センター) | ||
| 殺虫剤の基礎知識―業務用殺虫剤 | 日本防疫殺虫剤協会 | ||
| 殺虫剤の基礎知識―家庭用殺虫剤 | 日本家庭用殺虫剤工業会 | ||
| あかりまど | 人新世の地球――進行する全球都市化 | 井村 秀文(横浜市立大学 特任教授) | |
| 調査研究レポート | レジオネラ属菌が検出された薬草湯の指導について | 上田 淳司、藤澤 ゆかり、橋本 卓久(香川県東讃保健所) | |
| 特別寄稿 | 2014年に突然流行したデング熱―― 媒介蚊対策の重要性 | 小林 睦生(国立感染症研究所 名誉所員) | |
| 連載 | ■環境と経済 | 氏川 恵次(横浜国立大学) | |
| ■公衆浴場・温泉・旅館業・スポーツ施設・介護保険施設のための〈続〉よくわかるレジオネラ症対策 | 中臣 昌広(保健所・環境衛生監視員) | ||
| ■福島からの情報発信 | 佐藤 耕平(NPO法人いいざかサポーターズクラブ 理事) | ||
| ■散歩みち | 大森 節子(NPO法人C・キッズ・ネットワーク理事長) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2014年10月号 特集「巨大地震時における廃棄物・衛生対策」 |
|||
| 特集 | 巨大災害発生時における災害廃棄物対策のグランドデザインについて | 切川 卓也(環境省) | |
| 巨大地震発生時の災害廃棄物処理に備える計画づくり | 多島 良、大迫 政浩(国立環境研究所) | ||
| 宮城県における災害廃棄物処理 | 宮城県環境生活部震災廃棄物対策課 | ||
| 津波災害に伴う震災廃棄物等の処理について | 仙台市環境局 | ||
| 災害に伴う8,000ベクレル以下の廃棄物処理について〈福島県〉 | 鈴木 仁(福島県生活環境部) | ||
| 災害発生時のし尿処理及び衛生維持の課題について〈岩手県〉 | 沖田 潤一郎、成田 雄氣(岩手県環境生活部) | ||
| 災害廃棄物処理に必要な知識・技術を有する人材・育成について〈福岡市〉 | 真次 寛、篠原 弘人、簑原 知樹(福岡市) | ||
| 被災地における感染症対策 | 中島 一敏(東北大学病院) | ||
| 災害発生時の衛生動物対策 | 武藤 敦彦(日本環境衛生センター) | ||
| あかりまど | 日本人のこころとリサイクル | 吉岡 敏明(東北大学大学院) | |
| 調査研究レポート | レジオネラ属菌の迅速検査において偽陰性となる場合の取扱いについて | 高橋 朝子、郡山洋一郎、青木眞里子、大川 元(足立区足立保健所) | |
| 第58回生活と環境全国大会トピックス | 「環日本海地域における環境と地域エネルギーの活用」 テーマに富山市で開催 | 生活と環境全国大会事務局 | |
| 連載 | ■環境と経済 | 氏川 恵次(横浜国立大学) | |
| ■公衆浴場・温泉・旅館業・スポーツ施設・介護保険施設のための〈続〉よくわかるレジオネラ症対策 | 中臣 昌広(保健所・環境衛生監視員) | ||
| ■福島からの情報発信 | 渡辺 初治(大玉村社会福祉協議会常務理事兼事務局長) | ||
| ■散歩みち | 岡田 誠之(東北文化学園大学教授) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2014年9月号 特集「変化するごみ焼却施設の役割」 |
|||
| 特集 | 廃棄物処理施設整備をめぐる動向と今後の方向性について | 環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 | |
| エネルギー供給源としてのごみ焼却施設の現状と課題 | 高岡 昌輝(京都大学大学院) | ||
| 防災拠点としての廃棄物処理施設の現状と課題 | 宇野 晋(日本環境衛生施設工業会) | ||
| 地域エネルギー供給センターと災害に強い施設づくりを目指す「新武蔵野クリーンセンター」 | 木村 浩(武蔵野市) | ||
| 【対談】武蔵野市新クリーンセンター建設――“市民の声”を聴く 木村 文(武蔵野クリーンセンター運営協議会委員)× 藻谷 征子(武蔵野クリーンセンター運営協議会委員) (司会)小澤 紀美子(新武蔵野クリーンセンター(仮称)施設・周辺整備協議会会長、東京学芸大学名誉教授) |
|||
| 防府市クリーンセンター、バイオガスを用いた独立過熱器の運転報告 | 上原伸基、竹田航哉、内田博之、臼井勝久、服部孝一、杉原英雄(川崎重工業株式会社) | ||
| ごみ発電ネットワーク構想─ごみ発電のさらなる高度化を目指して― | 氷上 愛、伊藤 恵治、藤吉 秀昭(日本環境衛生センター) | ||
| あかりまど | 「ジャパン・モデル」の素晴らしさを実感―イギリス・オクスフォードから― | 松田 美夜子(生活環境評論家) | |
| 調査研究レポート | 衛生害虫に関する正しい知識の啓発用資材の開発と啓発手法の検討 | 上田 早穂(名古屋市健康福祉局生活衛生センター) | |
| 震災レポート | 大規模災害時における埋火葬のあり方について | 奥村 明雄(非営利活動法人日本環境斎苑協会理事長) | |
| 書評 | 『水道水質管理と水源保全――各国の制度と動向』を読んで | 評者・早川 哲夫(麻布大学教授) | |
| 連載 | ■環境と経済 | 山崎 圭一(横浜国立大学) | |
| ■公衆浴場・温泉・旅館業・スポーツ施設・介護保険施設のための〈続〉よくわかるレジオネラ症対策 | 中臣 昌広(保健所・環境衛生監視員) | ||
| ■福島からの情報発信 | 佐藤 奈緒子(有限会社すずらん工房) | ||
| ■環監未来塾 | 佐藤 清(テクノプラン建築事務所) | ||
| ■散歩みち | 藤村 コノヱ(認定NPO法人環境文明21共同代表) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2014年8月号 【通巻700号記念特集】 データでみる環境・衛生の60年 |
|||
| 特集 | 廃棄制約の時代を迎えて | 植田 和弘(京都大学大学院) | |
| 節足動物媒介性感染症、そ族・昆虫等の発生状況 | 小林 睦生(国立感染症研究所) | ||
| 生活衛生の動向と課題 | 大澤 元毅(国立保健医療科学院) | ||
| 火葬場の過去・現在・未来―その期待される役割― | 横田 勇(静岡県立大学名誉教授) | ||
| 廃棄物・3R政策の変遷と展望 | 大迫 政浩(国立環境研究所) | ||
| 大気環境と水環境の保全 | 坂本 和彦(埼玉県環境科学国際センター) | ||
| 有害汚染物質などからの環境保全の60年の歩みと現状、今日的課題 | 森田 昌敏(愛媛県環境創造センター) | ||
| 地球温暖化対策を振り返る | 柳下 正治(上智大学) | ||
| あかりまど | 国連ESDの10年 | 森嶌 昭夫(日本環境協会) | |
| 調査研究レポート | 地下式小規模受水槽の管理状況 | 村瀬 佳史(福岡市博多区保健福祉センター) | |
| 連載 | ■環境と経済 | 山崎 圭一(横浜国立大学) | |
| ■公衆浴場・温泉・旅館業・スポーツ施設・介護保険施設のための〈続〉よくわかるレジオネラ症対策 | 中臣 昌広(保健所・環境衛生監視員) | ||
| ■福島からの情報発信 | 永遠瑠 マリールイズ(NPO法人ルワンダの教育を考える会) | ||
| ■地域循環のいま | 岡本 昌也(一般社団法人地職住推進機構) | ||
| ■散歩みち | 森田 英樹(屎尿・下水研究会) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2014年7月号 特集「マダニを取り巻く環境とSFTS」 |
|||
| 特集 | 動物由来感染症に対する国の取り組み─最近話題となった節足動物媒介性感染症を中心に― | 福島 和子(厚生労働省健康局) | |
| 重症熱性血小板減少症候群とSFTSウイルス検出状況について | 濱崎千菜美、米満研三、高野愛、鍬田流星、下田宙、前田健(山口大学) | ||
| わが国におけるマダニ類の分布状況について | 沢辺 京子(国立感染症研究所) | ||
| 居住環境周辺にみられるマダニ類とその生態 | 大竹 秀男(宮城大学 教授) | ||
| マダニ類に対する効能・効果が承認された衛生害虫用殺虫剤ならびに忌避剤 | 數間 亨(日本環境衛生センター環境生物部) | ||
| あかりまど | 危惧される衛生害虫媒介性感染症への対応 | 武藤 敦彦(日本環境衛生センター環境生物部 部長) | |
| 調査研究レポート | レジオネラ症死亡事例と市内公衆浴場との関連調査について | 山田 秋津、佐藤 順子、春名 聡子、鳥居 芽衣、吉野 佑、今関 久和(船橋市保健所) | |
| 視点 | 生活衛生関係営業に対する振興施策に関する動向と基本的な視点 | 依田 泰(厚生労働省健康局) | |
| 環境レポート | 平成25年光化学大気汚染の概要について | 井土 八造(環境省水・大気環境局) | |
| 講演会レポート | “自然の聖地”とは何か〜「第1回山と自然の聖地の集い」に寄せて〜 | 松隈 豊(日本山岳協会・山と自然の聖地研究会) | |
| 連載 | ■環境と経済 | 長谷部 勇一(横浜国立大学大学院) | |
| ■公衆浴場・温泉・旅館業・スポーツ施設・介護保険施設のための〈続〉よくわかるレジオネラ症対策 | 中臣 昌広(保健所・環境衛生監視員) | ||
| ■福島からの情報発信 | 佐久間 秀夫(株式会社奥会津彩の里 代表取締役) | ||
| ■地域循環のいま | 角田 富雄(うどんまるごと循環コンソーシアム会長) | ||
| ■散歩みち | 鬼沢 良子(元気ネット事務局長) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2014年6月号 特集「進行する地球温暖化の影響と適応策」 |
|||
| 特集 | 気候変動の影響、適応等に関する最新の動向と我が国の対策 | 野本 卓也(環境省地球環境局) | |
| 地域が主体の気候リスク管理へ─― 緩和と適応の統合 | 西岡 秀三(地球環境戦略研究機関) | ||
| 海外における適応策の取組状況 | 久保田 泉(国立環境研究所) | ||
| 東京における気候変動対策の取組み | 小島 正禎(東京都環境局) | ||
| 横浜市における適応策の取組みと今後の展望 | 岩田 慶隆(前・横浜市温暖化対策統括本部) | ||
| 地球温暖化と節足動物媒介性感染症─― 世界と日本の現状 | 小林 睦生(国立感染症研究所) | ||
| 家庭でできる温暖化対策 | 金森 有子(国立環境研究所) | ||
| あかりまど | 気候変動の緩和と適応 | 浅野 直人(福岡大学法科大学院 教授) | |
| 調査研究レポート | 加温後に浴槽水のpH値が上昇した入浴施設におけるレジオネラ属菌の汚染防止指導について | 中島 貴代美、西川 裕二、西川 俊成、山本 恵子、椎名 有葵(埼玉県熊谷保健所)、棚倉 雄一郎、猪野 翔一朗(埼玉県本庄保健所)、大澤 浩一、持田 妙子(埼玉県秩父保健所) | |
| 国際展望 | 廃棄物処理の国際展開に向けて―アジア大洋州3Rフォーラムを踏まえて― | 熊谷 和哉(前・環境省廃棄物・リサイクル対策部) | |
| 連載 | ■環境と経済 | 氏川 恵次(横浜国立大学国際社会科学研究院) | |
| ■公衆浴場・温泉・旅館業・スポーツ施設・介護保険施設のための〈続〉よくわかるレジオネラ症対策 | 中臣 昌広(保健所・環境衛生監視員) | ||
| ■新公衆衛生概論―健康で快適な社会のために―《最終回》 | 欅田 尚樹(国立保健医療科学院) | ||
| ■福島からの情報発信 | 瓜生 泰弘(熱塩温泉山形屋代表取締役社長) | ||
| ■散歩みち | たいら 由以子(NPO法人循環生活研究所理事長) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2014年5月号 特集「くらしを守る化学物質管理」 |
|||
| 特集 | 化学物質による環境汚染の歴史的推移 | 鈴木 規之(国立環境研究所) | |
| WSSD2020年目標に向けた対応と今後の見通し─SAICMの実施等─ | 大井 通博(環境省環境保健部) | ||
| PRTR情報からみた暮らしの中の化学物質 | 亀屋 隆志(横浜国立大学大学院) | ||
| PRTR制度とリスクコミュニケーション | 寺沢 弘子(環境省事業化学物質アドバイザー) | ||
| 川崎市における化学物質による環境汚染の現状と対策 | 佐々田 丈瑠(川崎市環境局) | ||
| 利根川水系における水道水質事故を踏まえた対応 | 上迫 大介(厚生労働省健康局) | ||
| 花王におけるSAICMを踏まえた化学物質管理の取り組み | 服部 泰幸、小刀 慎司(花王株式会社) | ||
| あかりまど | 私と化学物質のリスク | 内山 巌雄(京都大学 名誉教授) | |
| 調査研究レポート | まつ毛エクステンションに関するアンケート調査 | 豊原 律子、久保田 悦子、仁平 晃司、斎藤 美稲、早見 研也、 田中 淳一、片岡 淳、小泉 惠一郎、國副 隆、広松 恭子(渋谷区保健所) | |
| 投稿 | 緊急時を想定した生活用水の確保とその手法―簡易ろ過器の効果と目的別水利用の考え方― | 原田 茂樹、尾崎 学、山本 武郎(宮城大学食産業学部) | |
| 連載 | ■環境と経済<新連載> | 山崎 圭一(横浜国立大学) | |
| ■環監未来塾<新連載> | 村瀬 誠(株式会社天水研究所) | ||
| ■地域循環のいま | 森 敦子(有限会社田代商店) | ||
| ■公衆浴場・温泉・旅館業・スポーツ施設・介護保険施設のための〈続〉よくわかるレジオネラ症対策 | 中臣 昌広(保健所・環境衛生監視員) | ||
| ■新公衆衛生概論―健康で快適な社会のために― | 秋葉 道宏(国立保健医療科学院) | ||
| ■福島からの情報発信 | 菊池 美保子(株式会社環境分析研究所) | ||
| ■散歩みち | 上 幸雄(NPO法人山のECHO) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2014年4月号 特集「アスベスト飛散防止の最新動向」 |
|||
| 特集 | 大気汚染防止法の一部改正の概要 | 渡辺 謙一(環境省水・大気環境局) | |
| 石綿含有建築物の解体等における労働者の石綿ばく露防止対策 | 樋口 政純(厚生労働省労働基準局) | ||
| 建築物石綿含有建材調査者制度の創設 | 野原 邦治(国土交通省住宅局) | ||
| アスベストの特性とその健康影響 | 柴田 英治(愛知医科大学医学部) | ||
| 解体・改修工事の際のアスベスト対策 | 川口 正人(清水建設株式会社技術研究所) | ||
| アスベストの気中濃度測定方法 | 豊口 敏之(株式会社環境管理センター) | ||
| 川崎市におけるアスベスト対策 | 藤田 周治(川崎市環境局環境対策部) | ||
| 震災時のアスベスト対策 | 早坂 昇(仙台市環境局環境部) | ||
| 建築物石綿含有建材調査者講習の概要 | 村岡 良介(日本環境衛生センター研修広報部) | ||
| あかりまど | アスベストには今後も注意が必要 | 神山 宣彦(東洋大学大学院 客員教授) | |
| 調査研究レポート | 民間委託による不法投棄パトロールの効果的運用について〜不法投棄マップの構築と活用〜 | 三枝 良輔、小澤 匡宏、岡 大真、小泉 明、西ヶ谷 友義(静岡県東部健康福祉センター) | |
| 震災レポート | 東日本大震災被災地の2年10カ月後の居住環境の実態について | 中臣 昌広(文京区文京保健所環境衛生監視員) | |
| 国際会議レポート | 第6回アジア3R自治体間ネットワーク会合の開催 「3R活動の評価手法」をメインテーマに、「都市ごみ・3R政策」「アジア都市間協力」について討論 | 「生活と環境」編集部 | |
| Special Interview | 新環境世代へのYELL(エール)<最終回> | 編集部 | |
| 連載 | ■公衆浴場・温泉・旅館業・スポーツ施設・介護保険施設のための〈続〉よくわかるレジオネラ症対策<新連載> | 中臣 昌広(保健所・環境衛生監視員) | |
| ■新公衆衛生概論―健康で快適な社会のために― | 小林 健一(国立保健医療科学院) | ||
| ■福島からの情報発信 | 佐原 禅(田村市復興応援隊 隊員) | ||
| ■散歩みち | 野間 紀之(NPO東海大学地域環境ネットワーク、環境カウンセラー) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2014年3月号 特集「循環産業の国際展開」 特別企画「平成26年度環境・衛生に係る予算案のポイント」 |
|||
| 特集 | 循環産業の国際展開について | 熊谷 和哉(環境省廃棄物・リサイクル対策部) | |
| 最近のアジア焼却炉商戦と廃棄物データ整備の現状 | 滝澤 元(日本環境衛生センター総局企画部) | ||
| 循環産業の途上国におけるビジネス展開について | 大野 正人(株式会社エックス都市研究所 代表取締役社長) | ||
| 静脈産業の新たな展開先としてのロシア | 新井 俊一(三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社) | ||
| ベトナムにおけるD-wasteの循環システム構築・展開事業について(FS事業事例) | 高野 友理(株式会社市川環境エンジニアリング) | ||
| 特別企画 | 環境省重点施策について | 『生活と環境』編集部 | |
| 生活衛生関係予算案等の概要 | 厚生労働省健康局生活衛生課 | ||
| 水道関係予算案について | 厚生労働省健康局水道課 | ||
| あかりまど | 循環産業の海外展開によせて | 藤田 正憲(大阪大学 名誉教授) | |
| 調査研究レポート | トコジラミ対策プロジェクトの取組みについて | 坂上 景子、大塚 圭輔、菅原 由佳、北野 晶子、菅原 弘行(札幌市保健所) | |
| 座談会 | 市町村における廃棄物技術の継承と人材育成<後篇> | ||
| Special Interview | 新環境世代へのYELL(エール) | 編集部 | |
| 連載 | ■新公衆衛生概論―健康で快適な社会のために― | 曽根 智史(国立保健医療科学院) | |
| ■福島からの情報発信 | 須釜 伸市(福島県県南保健福祉事務所) | ||
| ■環境衛生監視員の備忘録録<最終回> | 山田 満(元大阪府環境衛生監視員) | ||
| ■散歩みち | 横田 勇(静岡県立大学 名誉教授) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2014年2月号 特集「子どもの健康と環境を考える――エコチル」 |
|||
| 特集 | 子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)について | 高野 香子(環境省総合環境政策局環境保健部) | |
| エコチル調査の現況 | 米元 純三、新田 裕史(国立環境研究所「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」コアセンター)) | ||
| 子どもの健康と成長・発達 | 大矢 幸弘(国立成育医療研究センター生体防御系内科部医長) | ||
| 化学物質と子どもの健康 | 内山 巌雄(京都大学 名誉教授) | ||
| 広い地域にわかりやすく情報発信する北海道ユニットセンターの取り組み | 岸 玲子、土川 陽子(「子どもの健康と環境に関する全国調査」北海道ユニットセンター) | ||
| 規模の小ささを強みに変え、地域に密着して実施する鳥取ユニットセンターの取り組み | 大西 一成、福本 宗嗣(「子どもの健康と環境に関する全国調査」鳥取ユニットセンター) |
||
| 3県を管轄し、最も南にある南九州・沖縄ユニットセンターの取り組み | 加藤 貴彦(「子どもの健康と環境に関する全国調査」南九州・沖縄ユニットセンター) | ||
| エコチル調査の国際連携 | 中山 祥嗣、上島 通浩(エコチル調査国際連携調査委員会委員) | ||
| あかりまど | コトのはじまり――なぜ、環境教育をはじめたか | 小澤 紀美子(こども環境学会 会長、東京学芸大学 名誉教授) | |
| 調査研究レポート | 東日本大震災による井戸の異常発生アンケート調査及び災害時協力井戸の水質検査 | 松本 重裕、三部 光央、高澤 桂子、青山 博哉、新井 智幸、光畑 奈央子(町田市保健所生活衛生課) | |
| 座談会 | 市町村における廃棄物技術の継承と人材育成<前篇> | ||
| Special Interview | 新環境世代へのYELL(エール) | 編集部 | |
| 連載 | ■新公衆衛生概論―健康で快適な社会のために― | 緒方 一喜(日本環境衛生センター) | |
| ■福島からの情報発信 | 谷口 宏子(株式会社第一印刷、福の鳥プロジェクトプロデューサー) | ||
| ■環境衛生監視員の備忘録 | 山田 満(元大阪府環境衛生監視員) | ||
| ■散歩みち | 根本 康雄(NPO法人廃棄物政策フォーラム 理事) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2014年1月号 新春特集「着実に、持続可能な社会づくり」 特別企画「再生可能エネルギーと地域循環資源の活用 ――第57回生活と環境全国大会(香川大会)報告」 |
|||
| 特集 | 3Rが作る社会 | 炭谷 茂(恩賜財団済生会 理事長) | |
| 持続可能性のためのキーワード | 大澤 元毅(国立保健医療科学院 総括研究官) | ||
| 持続可能な社会づくりに向けて | 高岡 昌輝(京都大学大学院 教授) | ||
| 日本における金属資源循環型社会の在り方 | 中村 崇(東北大学多元物質科学研究所) | ||
| 新たな化石燃料の実用化と再生可能エネルギー | 内山 巌雄(京都大学 名誉教授) | ||
| 対談 これからの環境・衛生60年 | 加藤 三郎(NPO環境文明21)×松田 美夜子(生活環境評論家) | ||
| 特別企画 | 「第57回生活と環境全国大会」の全体概要について | 生活と環境全国大会事務局 | |
| 特別企画シンポジウム「香川県が秘める再生可能エネルギーの可能性」について | 橋本 大輔(日本環境衛生センター研修広報部) | ||
| 公開講座「生活環境をとりまく生物」について | 數間 亨(日本環境衛生センター環境生物部) | ||
| 公開講座「今! 廃棄物処理の現場で私たちが取り組んでいること」(第8回廃棄物処理施設維持管理技術事例研究発表会)について | 金子 勉(日本環境衛生センター環境工学部) | ||
| 公開講座「PM2.5による大気汚染の実態とその取り組み」について | 高橋 克行(日本環境衛生センター環境科学部) | ||
| 祝・環境大臣表彰「廃棄物・浄化槽研究開発功労者」 | |||
| 年頭所感 | 60年間培ったネットワークのさらなる発展へ | 奥村 明雄(日本環境衛生センター 理事長) | |
| 全力で取り組む環境行政の推進 | 石原 伸晃(環境大臣) | ||
| 健康で質の高い生活を送るための地域社会づくりを | 佐藤 敏信(厚生労働省健康局長) | ||
| 調査研究レポート | スーパー銭湯のレジオネラ対策の強化〜2段階方式の検査による効果的な衛生指導の実施〜 | 村井良次、伊藤敦子、田邉一明、小松雄幸、上野朋子(北九州市保健所)、 藤田景清、久保田勉、寺西泰司(北九州市環境科学研究所) | |
| 震災レポート | 仙台市における震災廃棄物等のリサイクルへの取組み | 遠藤 守也(仙台市環境局) | |
| 書評 | 『レジオネラ症対策のてびき』を読んで | 評者・野口 かほる(全国環境衛生職員団体協議会 会長) | |
| 連載 | ■新環境世代へのYELL(エール)<新連載> | 編集部 | |
| ■新公衆衛生概論―健康で快適な社会のために― | 欅田 尚樹(国立保健医療科学院) | ||
| ■福島からの情報発信 | 長澤 金一(福島県環境検査センター株式会社) | ||
| ■環境衛生監視員の備忘録 | 山田 満(元大阪府環境衛生監視員) | ||
| ■散歩みち | 松下 和夫(京都大学 名誉教授) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2013年 | |||
| 2013年12月号 特集「知っておきたい大気汚染問題」 特別企画「よくある害虫相談とその対応」 |
|||
| 特集 | PM2.5を中心とする最近の大気環境と健康影響について | 中井 里史(横浜国立大学大学院 教授) | |
| 大気質シミュレーションモデルと排出規制効果の算定 | 櫻井 達也(明星大学理工学部 助教) | ||
| 沿道における大気汚染対策技術の現状 | 下原 孝章(福岡県保健環境研究所) | ||
| 固定発生源による大気汚染の現状とその対策 | 柿沼 潤一(東京都環境科学研究所 所長) | ||
| 大気測定技術の現状と今後の動向 | 高橋 克行(日本環境衛生センター環境科学部) | ||
| アジア地域における大気環境保全に係る地域協力 | 藤田 宏志(環境省水・大気環境局大気環境課) | ||
| 大気汚染の改善に貢献した北九州市の市民活動 | 山下 俊郎(北九州市環境科学研究所 所長) | ||
| 特別企画 | 東京都における害虫相談の現況 | 片上 香織(東京都福祉保健局健康安全部) | |
| ハチ類の生態と被害および防除対策 | 金山 彰宏(元横浜市衛生研究所) | ||
| 家ネズミによる被害とその生態と対処方法 | 伊藤 靖忠(日本環境衛生センター環境生物部) | ||
| 都会のハシブトガラスとドバト―対策の考え方― | 松田 道生(野鳥研究家) | ||
| 大気汚染研究の現状と課題 | 若松 伸司(愛媛大学 教授) | ||
| 調査研究レポート | 太陽熱温水器で加温された給湯水によるレジオネラ症感染事例について | 三橋 徹 ほか(横浜市保健所) | |
| 連載 | ■新公衆衛生概論―健康で快適な社会のために― | 田島 昌樹(高知工科大学 准教授) | |
| ■福島からの情報発信 | 永石 正泰(JA新ふくしま技術参与) | ||
| ■環境衛生監視員の備忘録 | 山田 満(元大阪府環境衛生監視員) | ||
| ■散歩みち | 矢島 巖(環境共有コーディネーター) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2013年11月号 特集「環境衛生分野における開発途上国支援」 特別企画「水俣条約と水銀対策」 |
|||
| 特集 | 環境衛生分野における開発途上国支援──適正技術を根づかせるためには | 北脇 秀敏(東洋大学 副学長) | |
| 途上国の環境整備を支援する日本サニテーションコンソーシアム(JSC)の活動 | 太田 進、森田 昭(日本環境衛生センター) | ||
| NPOによる開発途上国のトイレ・衛生改善支援・ネットワーク活動 | 上 幸雄(日本トイレ研究所 理事) | ||
| 日本における環境衛生施設の技術・システムの変遷 | 河村 清史(元埼玉大学教授) | ||
| 〈ウンチ・ウンチク〉腸内細菌が寿命を決める! | 辨野 義己(理化学研究所) | ||
| 〈海外衛生見聞記〉フィリピン(マニラ近郊)の水廻り設備の実態 | 岡田 誠之(東北文化学園大学) | ||
| 特別企画 | 水銀に関する水俣条約の概要 | 金子 元郎(環境省総合環境政策局) | |
| 水俣条約の採択に伴う熊本県の対応 | 矢野 弘道(熊本県環境生活部) | ||
| 世界の水銀研究の今〜水銀国際会議2013に参加して〜 | 浅利 美鈴(京都大学環境科学センター) | ||
| あかりまど | ところ変われば…… | 桜井 国俊(沖縄大学 教授) | |
| 調査研究レポート | 特定建築物における最近の問題点と監視指導の方向性―ビルの管理体制の変化にともなう課題と対策― | 五味武人、板倉勝志、深谷慎一、本間絵美、阿部剣司、生駒憲一、十松佐恵(港区みなと保健所) | |
| RADIEX2013レポート | 放射能除染のフォーラム開催 | ||
| 連載 | ■新公衆衛生概論―健康で快適な社会のために― | 柳 宇(工学院大学 教授) | |
| ■福島からの情報発信 | 川村 博(特定非営利活動法人Jin代表) | ||
| ■環境衛生監視員の備忘録 | 山田 満(元大阪府環境衛生監視員) | ||
| ■散歩みち | 森田 英樹(屎尿・下水研究会幹事) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2013年10月 特集「3Rから2Rへ─リユースを推進する社会づくり─」 |
|||
| 特集 | 2Rをめぐる施策の情勢―第三次循環型社会形成推進基本計画の概要― | 山田 智子(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課) | |
| 製品リユースと循環型社会の形成 | 田崎 智宏(国立環境研究所) | ||
| 2Rの推進と社会システム─リユース容器を中心に─ | 安井 至(製品評価技術基盤機構理事長) | ||
| 長期間使用可能なリターナブル容器開発の取組み | 高橋 政彦、吉野 榮一(東洋ガラス株式会社) | ||
| 循環産業としてのリユース― 市場規模3兆円 | 加山 俊也(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社) | ||
| 今後のリユース業界に必要なこととリユース業界に対する思い | 波多部 彰(一般社団法人日本リユース機構(JRO)代表理事) | ||
| 日本リユース業協会の取り組み | 宮崎 隆(日本リユース業協会専務理事) | ||
| 町田市のリユースモデル事業における事業者との連携事例 | 谷 あずさ(町田市環境資源部) | ||
| 京都市におけるイベント等のエコ化の推進〜イベント等でのリユース食器の普及促進〜 | 山内 昌代(京都市環境政策局) | ||
| 学校牛乳でのリユースびん利用拡大の取り組み | 小沢 一郎(びんリユース推進全国協議会 事務局長) | ||
| 公共機関の会議での飲料提供時にびんを用いる動き | 中島 光(NPO団体World Seed 副代表理事) | ||
| 環境省におけるびんリユース、使用済製品等のリユースのモデル事業について | 水信 崇、鍋谷 芳比古(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部) | ||
| バイオリサイクルの時代 | 古市 徹(北海道大学 名誉教授) | ||
| 調査研究レポート | アスベスト除去作業の立入検査において適切な指導を実施するための取り組み | 尾藤 孝弘、堅田 将太、宮城島 利英、高梨 千穂、杉井 邦好、西ヶ谷 友義(静岡県東部健康福祉センター) | |
| 第57回生活と環境全国大会トピックス | 「再生可能エネルギーと地域循環資源の活用」テーマに高松市で開催 | 生活と環境全国大会事務局 | |
| 連載 | ■新公衆衛生概論―健康で快適な社会のために― | 鍵 直樹(東京工業大学大学院 准教授) | |
| ■福島からの情報発信 | 佐藤 彌右衛門(いいたてまでいの会 幹事長) | ||
| ■環境衛生監視員の備忘録 | 山田 満(元大阪府環境衛生監視員) | ||
| ■散歩みち | 岡田 誠之(東北文化学園大学 教授) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2013年9月号 特集「海ごみ対策の円滑な推進に向けて」 |
|||
| 特集 | 海岸漂着物の実態とその対策 | 多田 佐和子(環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室) ) | |
| 海ごみの科学─漂流・漂着のメカニズムと研究の最前線─ | 磯辺 篤彦(愛媛大学沿岸環境科学研究センター 教授) | ||
| 全国で展開する海岸美化活動 | 福田 賢吾(公益財団法人海と渚環境美化・油濁対策機構) | ||
| 対馬市における海岸漂着物の現状と対策について | 田口 憲一(対馬市市民生活部環境政策課) | ||
| 山形県における漂流・漂着物の実態とその対策 | 会田 健(山形県境エネルギー部循環型社会推進課) | ||
| 海域・陸域一体となった海ごみ対策〈香川県〉 | 大倉 恵美(香川県環境森林部環境管理課) | ||
| 瀬戸内海(香川県)における海岸、河岸ごみの実態〜20回目のNPO活動〜 | 河崎 素子(アースデイinあじ・水ぎわクリーン作戦事務局) | ||
| 宮古沖から放流した模擬ごみがオレゴン州に | 田中 勝(鳥取環境大学サスティナビリティ研究所 所長) | ||
| 調査研究レポート | 産業廃棄物中間処理業者における再生処分に関する一考察 | 伊藤 靜、馬渕 博、志村 真紀、太田 茂、沼野 秀美、内藤 弘、齋藤 博(静岡県中部健康福祉センター) | |
| 水環境レポート | 水産業と外来生物のかかわり | 中野 喜央(いであ株式会社国土環境研究所) | |
| 連載 | ■新公衆衛生概論―健康で快適な社会のために― | 大澤 元毅(国立保健医療科学院 統括研究官) | |
| ■ブダペストこぼれ話 <最終回> | 小野川 和延(元 中東欧地域環境センター 次長) | ||
| ■福島からの情報発信 | 藤田 恒雄(福島県水産試験場漁場環境部長) | ||
| ■環境衛生監視員の備忘録 | 山田 満(元大阪府環境衛生監視員) | ||
| ■散歩みち | 井村 秀文(横浜市立大学 特任教授) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2013年8月 特集「火葬場問題の現状と課題」 |
|||
| 特集<総論> | 火葬場をめぐる諸問題 | 奥村 明雄(日本環境斎苑協会 理事長) | |
| 特集<火葬場整備のあり方> | 火葬場建設に伴う計画策定と諸手続き | 泊瀬川 孚(日本環境斎苑協会 事務局長) | |
| 火葬場における有害物質の現況と対策 | 高岡 昌輝(京都大学大学院 教授)、大下 和徹(京都大学大学院 准教授) | ||
| 火葬場の建築・環境整備 | 鈴木 哲(株式会社アール・アイ・エー東北支社) | ||
| 火葬炉の構造と維持管理 | 石黒 秀幸(株式会社宮本工業所) | ||
| 火葬場と火葬炉設備 | 吉川 均(富士建設工業株式会社) | ||
| 特集<大震災と広域火葬のあり方> | 震災時における埋火葬の広域的対応の現状 | 横田 勇(静岡県立大学 名誉教授) | |
| 大震災と埋火葬広域対応について | 赤尾 牧夫(宮城県保健環境センター 所長) | ||
| 東京都の広域火葬計画及び関係機関と連携した取組みについて | 野口 かほる(東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課 ) | ||
| あかりまど | 東日本大震災と南海トラフ地震への対応 | 奥村 明雄(日本環境衛生センター 理事長) | |
| 調査研究レポート | プールにおける安全対策の強化〜塩素ガス発生事故への備え〜 | 黒澤 智恵(多摩府中保健所) | |
| 海外環境レポート | インドネシア廃棄物事情余話 | 滝澤 元、宮川 隆(日本環境衛生センター総局企画部企画国際室) | |
| 連載 | ■新公衆衛生概論―健康で快適な社会のために― | 秋山 茂(元北里大学医療衛生学部) | |
| ■ブダペストこぼれ話 | 小野川 和延(元 中東欧地域環境センター 次長) | ||
| ■福島からの情報発信 | 大村 卓(福島環境再生事務所長) | ||
| ■環境衛生監視員の備忘録 | 山田 満(元大阪府環境衛生監視員) | ||
| ■散歩みち | 松島 肇(浜松医科大学 名誉教授) | ||
| 2013年7月 特集「廃止ごみ焼却施設の解体に向けた取り組み」 |
|||
| 特集 | 廃棄物処理施設整備計画について | 坂口 芳輝(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課) | |
| 東京二十三区清掃一部事務組合における焼却炉解体 | 西山 正彦(東京二十三区清掃一部事務組合建設部建設課) | ||
| ごみ減量に伴う廃止炉解体について | 米村 卓郎(横浜市資源循環局施設課) | ||
| 廃止焼却施設の解体事例〜解体の背景、解体までの手続き、解体方法・その工夫等〜 | 酒井 祐介((株)熊谷組プロジェクトエンジニアリング室) | ||
| 廃止焼却施設解体事業に伴う留意事項 | 佐藤 幸世(日本環境衛生センター 環境工学部) | ||
| あかりまど | 身に合った服か服に身を合わせるか | 武田 信生(京都大学 名誉教授) | |
| 調査研究レポート | レジオネラ症発生届に伴う公衆浴場指導事例について | 藤井 恵子、篠宮 哲彦(埼玉県東松山保健所)、嶋田 直美、福島 浩一、青木 敦子(埼玉県衛生研究所) | |
| 災害廃棄物レポート | 東日本大震災に伴う災害廃棄物等の処理の進捗状況 | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 | |
| 除染調査報告 | 汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況調査結果(第3回)について | 環境省水・大気環境局除染チーム | |
| 視点 | ランプにおける水銀含有量削減の取り組みについて | 田村 暢宏(日本照明工業会) | |
| PCOアピール | 6/4〜7/4は「ムシナシ月間(ねずみ・衛生害虫駆除推進月間)」です! | 公益社団法人日本ペストコントロール協会 | |
| 連載 | ■新公衆衛生概論―健康で快適な社会のために― | 遠藤 卓郎(国立感染症研究所 名誉所員) | |
| ■ブダペストこぼれ話 | 小野川 和延(元 中東欧地域環境センター次長) | ||
| ■福島からの情報発信 | 梅宮 勇造(NPO法人負けないぞ福島宣言!プロジェクト理事長) | ||
| ■環境衛生監視員の備忘録 | 山田 満(元大阪府環境衛生監視員) | ||
| ■散歩みち | 百瀬 則子(ユニー(株)業務本部環境社会貢献部部長) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2013年6月 特集「超高齢社会における環境福祉のまちづくり」 |
|||
| 特集 | 持続可能な福祉都市―― 高齢化時代のまちづくりにおける「環境と福祉」の統合 | 広井 良典(千葉大学 法経学部 教授) | |
| 長寿社会のまちづくりプロジェクト――千葉県柏市豊四季台地域の事例 | 柏市保健福祉部福祉政策室 | ||
| 災害公営住宅「相馬井戸端長屋」について | 松田 早苗(相馬市健康福祉課) | ||
| 都市の低炭素化の促進について〜エコまち法制定の概要〜 | 高橋 慶(国土交通省都市局都市計画課) | ||
| あかりまど | 超高齢社会における環境福祉のまちづくり | 炭谷 茂(恩賜財団済生会 理事長) | |
| 調査研究レポート | 人工炭酸泉装置を使用した浴槽水における過マンガン酸カリウム消費量の推移について | 宮地 孝昌、森田 典義、佐藤 千歳、中山 貴喜、大竹 弘俊、伊藤 盛康、犬塚 君雄(岡崎市保健所) | |
| 解説 | 越境大気汚染問題の現状と課題 | 鈴木 克徳(金沢大学環境保全センター長・教授) | |
| 特別寄稿 | 大阪湾フェニックスセンター設立30周年を迎えて | 矢野 久志(大阪湾広域臨海環境整備センター常務理事) | |
| 連載 | ■新公衆衛生概論―健康で快適な社会のために―<新連載> | 欅田 尚樹(国立保健医療科学院生活環境研究部長) | |
| ■ブダペストこぼれ | 小野川 和延(元 中東欧地域環境センター次長) | ||
| ■福島からの情報発信 | 国分 真一(特定非営利活動法人超学際的研究機構 事務局長) | ||
| ■環境衛生監視員の備忘録 | 山田 満(元大阪府環境衛生監視員) | ||
| ■散歩みち | 秋元 智子(環境カウンセラー) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2013年5月 特集「再生可能エネルギーの最新動向」 |
|||
| 特集 | 再生可能エネルギー拠点としての廃棄物発電 | 高岡 昌輝(京都大学大学院 教授) | |
| 再生可能エネルギー創出に向けたバイオマス利活用技術の動向 | 藤田 正憲(大阪大学 名誉教授) | ||
| ごみ発電電気事業者からみたFIT | 千歳 昭博(東京エコサービス株式会社) | ||
| 北九州市の再生可能エネルギー推進に向けた普及啓発の取組み | 村上 恵美子(北九州市環境局環境未来都市推進室) | ||
| 再生可能エネルギー固定価格買取制度における調達価格の動向 | 石坂 朋久(環境新聞社) | ||
| あかりまど | グリーン・エコノミーから持続可能な発展へ | 植田 和弘(京都大学大学院 教授) | |
| 調査研究レポート | 産業廃棄物不適正保管の解消に向けた排出事業者に対する新たな取り組み | 綿野 尚幸、三枝 良輔、中田 尋久、小泉 明、斉藤 博、西ヶ谷 友義(静岡県東部健康福祉センター) | |
| 解説 | 重症熱性血小板減少症候群とは | 山岸 拓也、西條 政幸(国立感染症研究所感染症疫学センター) | |
| 視点 | 東京都における水銀処理等の取り組みについて | 金子 亨(東京都環境局廃棄物対策部) | |
| 環境調査報告 | 家庭エコ診断における地域別CO2排出量の推計と削減対策の分析 | 川原 博満、中垣 藍子、菊井 順一(地球温暖化防止全国ネット) | |
| 震災レポート | 東日本大震災被災地の1年10カ月後の居住環境の実態について | 中臣 昌広(文京区文京保健所) | |
| 国際会議レポート | 第5回アジア3R自治体間ネットワーク会合の開催─「都市ごみ・3R政策」「技術移転」について討論 | 生活と環境編集部 | |
| 連載 | ■ブダペストこぼれ話 | 小野川 和延(元 中東欧地域環境センター次長) | |
| ■福島からの情報発信 | 片寄 久巳(福島県生活環境部) | ||
| ■環境衛生監視員の備忘録 | 山田 満(元大阪府環境衛生監視員) | ||
| ■散歩みち | 松永 はつ子(トイレ壁画デザイナー) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2013年4月 特集「使用済家電等不用品回収業者の実態と対策」 |
|||
| 特集 | 違法な不用品回収業者問題について | 眼目 佳秀(環境省廃棄物リサイクル対策部リサイクル推進室) | |
| 岡山市における不用品回収業者対応 | 中田 智志(岡山市環境局環境事業課) | ||
| 北九州市における不用品回収業者への対応事例 | 青? 祐治(北九州市環境局環境監視部) | ||
| 埼玉県における不用品回収業者対策について | 櫻井 卓(埼玉県環境部資源循環推進課) | ||
| 富山県における家電品等無料回収業者への県下一斉立入調査について | 猪俣 智浩(富山県生活環境文化部環境政策課) | ||
| 京都府における使用済家電製品の不適正処理対策について | 岩城 吉英(京都府文化環境部環境・エネルギー局循環型社会推進課) | ||
| 長谷工グループにおけるマンションの中古品の買取り・回収、リユース再販売の状況 | 樋口 邦彦(株式会社カシコシュ 代表取締役) | ||
| 廃棄物に該当する使用済家電製品の不法輸出対策について | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室 | ||
| 家電スクラップの違法輸出水際対策最前線 | 中野 正博(中国四国地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課) | ||
| 金属スクラップ積載船からの火災への対策について | 西園 直雄(海上保安庁警備救難部刑事課) | ||
| 使用済電気電子機器の輸出に伴う諸課題 | 寺園 淳(国立環境研究所) | ||
| 不要品回収業と法規制 | 長岡 文明(BUN環境課題研修事務所) | ||
| あかりまど | 31年目のフェニックス事業に学ぶべきこと | 三本木 徹(日本環境衛生センター常務理事・総局長) | |
| 調査研究レポート | ダニアレルゲン量等調査結果について(12年間のまとめ) | 奥貫 智子、河村 昌輝、石黒 誠、篠田 崇徳(名古屋市生活衛生センター) | |
| 環境教育レポート | 子どもたちの輝き〜体験型サイエンス教室のススメ〜 | 小島 昭(群馬工業高等専門学校 特命教授) | |
| 環境省告示 | 「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年環境庁告示第13号)の改正について[最終改正:平成25年2月21日環境省告示第9号 | 胡桃澤 博司(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課) | |
| 連載 | ■ブダペストこぼれ話 | 小野川 和延(元 中東欧地域環境センター次長) | |
| ■福島からの情報発信 | 渡邉 宗史(特定非営利活動法人オン・ザ・ロード福島支部事務局長) | ||
| ■環境衛生監視員の備忘録<新連載> | 山田 満(元大阪府環境衛生監視員) | ||
| ■散歩みち | 秋元 智子(環境カウンセラー) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2013年3月 特集「身の回りの特定外来生物」 緊急企画「平成25年度環境・衛生に係る予算案のポイント」 |
|||
| 特集 | アルゼンチンアリ― 足もとの侵略種─ | 頭山 昌郁(日本蟻類研究会) | |
| アライグマ問題を教訓にして私たちは何を学ぶべきか― 個体群動態の研究から― | 淺野 玄(岐阜大学応用生物科学部 準教授) | ||
| 危険生物セアカゴケグモについて | 吉田 政弘(いきもの研究社 代表) | ||
| 特定外来種クリハラリス(タイワンリス)の野生化とその影響 | 林 典子(森林総合研究所) | ||
| 緊急企画 | 環境省重点施策について | 環境省廃棄物・リサイクル部廃棄物対策課 | |
| レアメタル等を含む小型電子機器等リサイクル推進事業費について | 眼目 佳秀(環境省廃棄物・リサイクル部リサイクル推進室) | ||
| 災害廃棄物処理事業費等について | 『生活と環境』編集部 | ||
| 再生可能エネルギー導入事業費等について | 『生活と環境』編集部 | ||
| 生活衛生課予算(案)の概要 | 厚生労働省健康局生活衛生課 | ||
| 水道関係予算案について | 厚生労働省健康局水道課 | ||
| あかりまど | 津波を経た生態系の向かう先 | 永幡 嘉之(自然写真家) | |
| 調査研究レポート | ミスト発生設備に関する実態調査について | 榊原 大輔(愛知県衣浦東部保健所) | |
| ■地域でつながる環境活動 | 植村 芳弘(光市快適環境づくり推進協議会 会長) | ||
| ■ブダペストこぼれ話 | 小野川 和延(元 中東欧地域環境センター次長) | ||
| ■福島からの情報発信 | 宍戸 義広(生活協同組合コープふくしま 常務理事) | ||
| ■環監一直線!<最終回> | 奥村 龍一(東京都多摩府中保健所) | ||
| ■トイレで社会を変える<最終回> | 上 幸雄(日本トイレ研究所) | ||
| ■環境と数学<最終回> | 横田 勇(静岡県立大学 名誉教授) | ||
| ■散歩みち | 池上 三喜子(公益財団法人市民防災研究所 理事) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2013年2月 特集「これからの環境衛生監視」 |
|||
| 特集 | 今後の地域保健対策のあり方――地域保健対策検討会の概要 | 林 謙治(国立保健医療科学院前院長、地域保健対策検討会座長) | |
| 環境衛生監視員の人材確保と育成について | 大澤 元毅(国立保健医療科学院 統括研究官) | ||
| 生活衛生分野における今後の環境衛生監視について〜東京都の取り組みから〜 | 仁科 彰則(東京都健康安全研究センター広域監視部長) | ||
| 今後の地域保健対策と環境衛生監視員―現場で求められる三つの要素― | 中臣 昌広(文京区文京保健所 生活衛生課) | ||
| 住民が望む健康的な居住環境に向けた環境衛生監視員の役割(住まいと健康フォーラムの活動から) | 五味 武人(港区みなと保健所 生活衛生課) | ||
| 大震災発生時の環境衛生対策とその人材育成―環境衛生監視員の役割と求められる能力― | 鈴木 晃(国立保健医療科学院 統括研究官) | ||
| 環境衛生行政を担う人材に求められること | 野口 かほる(全国環境衛生職員団体協議会会長、東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課長) | ||
| 続報 第55回生活と環境全国大会 | 公開シンポジウム 大災害時における環境衛生対策「東日本大震災から1年半の現状と課題」 | 編集部 | |
| 視点 | 海外における水銀対策の状況について(EUの取り組み) | 高岡 昌輝(京都大学大学院 教授) | |
| 調査研究レポート | 文京区における公衆浴場等シャワー水のレジオネラ症発生防止対策の成果 | 岡部 咲子、中臣 昌広、山下靖之、杉本 麻里子、石山 康史(文京区文京保健所) | |
| 連載 | ■ブダペストこぼれ話 | 小野川 和延(元 中東欧地域環境センター次長) | |
| ■福島からの情報発信 | 八島 信夫(株式会社福島建設工業新聞社 顧問) | ||
| ■環監一直線! | 奥村 龍一(東京都多摩府中保健所) | ||
| ■トイレで社会を変える | 上 幸雄(日本トイレ研究所 代表理事) | ||
| ■環境と数学 | 横田 勇(静岡県立大学 名誉教授) | ||
| ■散歩みち | 犬伏 由利子(消費科学センター 理事) | ||
| ■東西南北 | |||
| 2013年1月 新春特集「環境・衛生の近未来――1000文字の提言」 特別企画「地域循環とエネルギーを考える――第56回生活と環境全国大会(愛知大会)報告」 |
|||
| 特集 | 阿部 孝夫(川崎市長) | ||
| 大垣 眞一郎 (国立環境研究所理事長) | |||
| 加藤 三郎(NPO法人環境文明21共同代表、環境文明研究所所長) | |||
| 小澤 紀美子(東京学芸大学名誉教授、東海大学教授) | |||
| 小林 睦生(国立感染症研究所名誉所員) | |||
| 酒井 伸一(京都大学教授) | |||
| 崎田 裕子(ジャーナリスト・環境カウンセラー、NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット理事長) | |||
| 鈴木 克徳(金沢大学教授) | |||
| 永島 徹也(環境省廃棄物・リサイクル対策部) | |||
| 古川 実(日本環境衛生施設工業会会長) | |||
| 森田 昌敏(愛媛大学客員教授) | |||
| 山本 和夫(東京大学教授) | |||
| 吉川 廣和(前・日本経済団体連合会環境安全委員会廃棄物・リサイクル部会部会長) | |||
| 特別企画 | 「第56回生活と環境全国大会」の全体概要について | 生活と環境全国大会事務局 | |
| 次期開催は高松市で〜大会式典の挨拶より〜 | 久保 英一郎(香川県健康福祉部生活衛生課長)) | ||
| 特別企画シンポジウム「循環資源の活用による再生可能エネルギーと地域活性化を考える」について | 齊藤 眞(日本環境衛生センター企画部) | ||
| 公開講座「衛生害虫に関する最近の話題」について | 橋本 知幸(日本環境衛生センター環境生物部) | ||
| 公開講座「廃棄物処理施設の適正な維持管理に向けて」(第7回廃棄物処理施設維持管理技術事例研究発表会)について | 藤原 周史(日本環境衛生センター環境工学部) | ||
| 公開講座「私たちの暮らしと大気汚染」について | 高橋 克行(日本環境衛生センター環境科学部) | ||
| 「生活と環境展示会」について | 生活と環境全国大会事務局 | ||
| 「生活と環境展示会」に出展して〜ふろしきからの環境メッセージ〜 | 浜口 美穂(ふろしき研究会会員・3R推進マイスター) | ||
| 年頭所感 | 大きな転換期に向けさらに挑戦を | 奥村 明雄(日本環境衛生センター 理事長) | |
| 廃棄物の循環利用・適正処理の推進に向けた新たな展開 | 梶原 成元(環境省廃棄物・リサイクル対策部長) | ||
| 衛生的で快適な国民生活の実現に向け取り組む | 矢島 鉄也(厚生労働省健康局長) | ||
| 海外衛生見聞記 | モスクワ市内のトイレ事情 | 岡田 誠之(東北文化学園大学 教授) | |
| 連載 | ■ブダペストこぼれ話 | 小野川 和延(元 中東欧地域環境センター次長) | |
| ■低炭素社会と地域の活性化<最終回> | 大歳 恒彦(元東北公益文科大学 教授) | ||
| ■福島からの情報発信 | 早川 哲郎(市民活動団体連携復興プロジェクト会議・情報センター 事務局長) | ||
| ■環監一直線! | 奥村 龍一(東京都多摩府中保健所) | ||
| ■トイレで社会を変える | 上 幸雄(日本トイレ研究所代表理事) | ||
| ■環境と数学 | 横田 勇(静岡県立大学名誉教授) | ||
| ■散歩みち | 河村 清史(埼玉大学大学院教授) | ||
| ■東西南北 | |||
カテゴリー
Group
Ranking
-

No.1
令和2年版 廃棄物処理法の解説
5,200円(税込5,720円)
-

No.2
図解 廃棄物処理法
2,000円(税込2,200円)
-

No.3
令和2年版 廃棄物処理法の解説/令和7年版 廃棄物処理法法令集 3段対照(2冊セット)
8,700円(税込9,570円)
-

No.4
令和7年版 廃棄物処理法法令集 3段対照
4,000円(税込4,400円)
-

No.5
土日で入門 廃棄物処理法〈第9版〉
1,819円(税込2,000円)
Other page
日本環境衛生センター
出版担当
*事前に見積書をご希望の方、まとめ買い(50冊以上割引あり)をご希望の方は、上のサイドメニューの[Contact お問い合わせ]、または各書籍ページの[この商品について問い合わせる]より事前にお問い合わせください。
*FAXでも注文を受け付けております。
お名前・ふりがな・郵便番号・住所・電話番号・FAX番号・請求書の日付の要不要および送料を書籍代に含めるか含めないかを明記の上、下記FAX番号まで送信ください。
*購入完了後、自動で確認メールが送信されます。万が一届かない場合は、当センター出版担当までご連絡ください。
一般財団法人日本環境衛生センター
サステナブル社会推進部
出版担当
TEL: 044-288-4967
FAX: 044-288-4952
Email: shuppan@jesc.or.jp